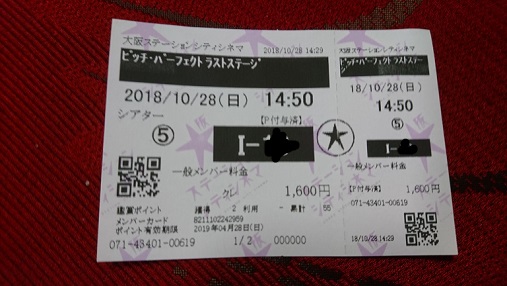THE DUFF/ダメ・ガールが最高の彼女になる方法 60点
2018年11月5日 レンタルDVD鑑賞
出演:メイ・ホイットマン ベラ・ソーン ロビー・アメル アリソン・ジャネイ
監督:アリ・サンデル

近所のTSUTAYAで『 アラサー女子の恋愛事情 』の隣にあったので、カバー裏のあらすじを読むこともなく、タイトルだけで借りてきた。THE DUFFとは何ぞや?なにやらダメ系女子の匂いがするが・・・という好奇心だけでレンタルを決断するに十分なインパクトのタイトルである。
あらすじ
ビアンカ(メイ・ホイットマン)とジェスとキャシーは仲良し3人組。しかし、親戚のイケメン・フットボーラーのウェスリー(ロビー・アメル)から「お前はDUFF(=Designated Ugly Fat Friend=)だ」と言われ、大ショック。親友とは一方的に絶交し、さらにはスクール・カースト頂点のマディソン(ベラ・ソーン)に目をつけられてしまう。しかし、ふとしたきっかけからウェスリーに化学を教えるのと交換条件に、どうすればイケてる女子になれるのかコーチングしてもらうことになり・・・
ポジティブ・サイド
まず、アラサーにして女子高生役を演じきったメイ・ホイットマンに最大級の敬意を表したい。『 JUNO ジュノ 』にしてもそうだが、アメリカの学園ドラマ、もしくはティーン映画は、必ずしも美少女というものをフィーチャーしない。日本とは対照的だ。アメリカで尊ばれる女子は、チアのキャプテンを務めて、フットボール部のQBと付き合うような典型的なイケてる系の女子と、自らの意思と能力で道を切り拓いてく self-starter に大別されるようだ。前者の典型がマディソンで、後者の典型がビアンカというわけである。ホイットマンの年齢と見た目のギャップがなければ、逆に本作のビアンカという nerdy にして slutty であるというキャラは成立しなかったかもしれない。それほど彼女の演技は光っている。というか、異彩を放っている。
異彩と言えば、『 ミッドナイト・サン タイヨウのうた 』の主演を張ったベラ・ソーンの腐れ外道っぷりも見逃せない。フレネミーという言葉では生ぬるい、目があっただけで敵であると認識する/されるような関係を学校のあちこちで築いている。本当に同じ役者かと思うぐらいで、若い似合わず演技力の幅を感じさせる。しかし、演技の幅と言えば、日本にも浜辺美波がいる。
逆に、母親役をやらせればこの人の右に出る者なし、というアリソン・ジャネイはその安定した存在感を発揮する。離婚受容プロセスの5段階セミナーには笑うしかない。母と娘の底抜けに明るく、それでいて陰のある会話劇に、日本では失われて久しい親子の対話を見るようだ。
本作は cyber bullying =ネットいじめの怖さを面白おかしく描き出す。ストーリー上では、かなりご都合主義的な力技で解決してしまうが、現実ではこうはならない。2015年に全世界的にバズったDover Police DashCam Confessional (Shake it Off)という動画を観て、今も覚えているという人も多いだろう。これはかなり好意的に受け止められた面白動画だが、実際にティーンが同じようなことをしている映像がネット世界にアップされてしまえば、もうどうしようもない。そうした意味では、本作を教育目的に観ることもできるのである。予定調和的な世界であるが、だからこそ安心して楽しめるロマンティック・コメディである。
ネガティブ・サイド
人と人との距離感は、人によって異なる。しかし、本作はかなり強烈なDUFF脱却トレーニングを課してくる。自分が同じポジションにいたとして、こんなことができるだろうかと思わされる描写もあった。なにより見知らぬ他人に迷惑をかけることになる。荒療治と言えばそれまでだが、ホラー映画好きのナード女子という設定がもう一つ活かされないのは残念である。
また、ウェスリーのキャラクターがあまりにも爽やかで、それでいてかなりの下衆でもある。人によっては、途中で見るのを辞めてしまうかもしれない。特にクライマックスのホームカミングでの行動は、下手をすると一生残るトラウマを与えかねない鬼畜の所業である。もちろん、「それで良い!」という声も上がって然るべきだし、「さすがにやり過ぎだろう」という声も聞こえてきそうだ。ちなみにJovianは後者である。
総評
目線をどこに置くかで本作の評価はかなり割れるというか、異なるだろう。学園ドラマとして見るなら凡作になるのかもしれないが、ダイバーシティを重んじ、なおかつ軽んじるアメリカ社会の縮図を本作に見出すのなら、居場所を見出せないマイノリティにも、チャンスはあるというメッセージであるとも解釈できる。日本で鑑賞される際にはそこまで考える必要はないだろうが、ネットいじめの怖さやスクール・カーストの問題点などを抉る物語でもある。中高生を子に持つ親が子どもと一緒に鑑賞してみるのも存外に楽しいかもしれない。