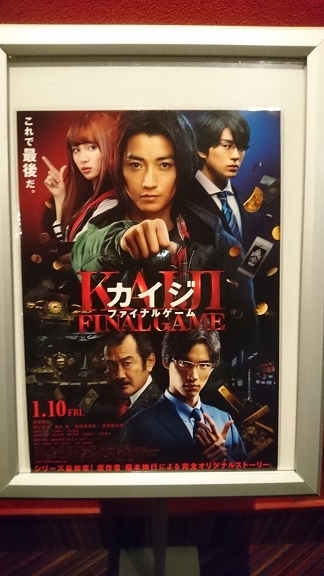母なる証明 90点
2020年2月16日 シネマート心斎橋にて鑑賞
出演:キム・ヘジャ ウォンビン
監督:ポン・ジュノ

『 スノーピアサー 』に続いて、シネマート心斎橋にて鑑賞。これも以前にWOWOWで観たんだったか。しかし、再度の鑑賞をしてみると違った風景が見えてくる。これが再鑑賞の面白いところ。

あらすじ
軽度の知的障がいを持つトジュン(ウォンビン)は、近所の女子高生の殺害容疑で警察に逮捕されてしまった。母(キム・ヘジャ)は息子の無実を証明すべく、独りきりで事件を調査していくが・・・

ポジティブ・サイド
冒頭のEstablishing Shotの美しさよ。乾いた空気の草原に木が一本だけ佇立している。その向こうには林があり、外界の視線からは完全に遮断されている。その場で踊り始める母の姿は『 ジョーカー 』のトイレでダンス・シーンを思い起こさせた。『 ジョジョ・ラビット 』のエルサの言葉を借りるまでもなく、ダンスとは自己表現である。無表情で踊る母の姿に、我々は虚無感と歓喜の両方を見出す。非常に美しく、そして示唆的なオープニングである。
母親が息子のために孤軍奮闘、奔走する様は『 ベン・イズ・バック 』のジュリア・ロバーツが神がかり的な演技を見せたが、本作のキム・ヘジャはそれに勝るとも劣らないパフォーマンスを披露してくれた。この母親、名前がない。いや、あるはずだが、それが劇中で呼ばれることは一切ない。名前が呼ばれないキャラクターは時々いる。『 用心棒 』の三船敏郎や『 荒野の用心棒 』、『 夕陽のガンマン 』、『 続・夕陽のガンマン 』のクリント・イーストウッドらがそれである。彼らにも名前はあるが、それらは便宜上のもので、そこに本質的な意味はない。「名は体を表す」と言うが、名が無い者は行動で体を表すしかない。その恐るべき行動力で、役立たずの警察や弁護士を振り切り、韓国社会の一種の闇に切り込んでいく。キム・ヘジャ演じる“母”が『 ベン・イズ・バック 』のジュリア・ロバーツに勝ると思われる点は、母なき者に涙を流すことができるところである。ジュリア・ロバーツは我が子ではない他人を容赦なく、躊躇なく地獄に落とすような真似をするが、この母は母親としての普遍的な情を持っている。それが良いか悪いかは別にして、「女は弱し、されは母は強し」を実現し、そして実践している。
本作は様々なシーンが伏線であり、重要な前振りとなっている。特に冒頭のダンス・シーンの直後の「血」は、単純ではあるが、強力な伏線である。ミステリ要素が強く、まるで邦画『 二重生活 』のようなシーンもある(というか、『 二重生活 』の一部シーンが本作にインスパイアされた可能性があると言うべきか)。非常に基本的なことであるが、伏線にはインパクトが必要で、ポン・ジュノ監督はそれを反復という形で表現する。本作における「血」に代表される一連のモチーフは、さりげなく、しかし周到に張り巡らされている。ミステリ愛好家も納得させうる構成になっていると感じる。
『 パラサイト 半地下の家族 』と同じく、本作も途中でトーンがガラリと変わる。ミステリ/サスペンスだったはずが、ある瞬間がホラーなのである。特にトジュンとアジョンの遭遇シーンの闇。闇とは不思議なもので、実体がない、単に光が欠如した空間であるにも関わらず、圧倒的な存在感を持つことがある。『 パラサイト 半地下の家族 』でも、壁の向こうには闇が広がっていた。同じく、懐中電灯に照らし出される老婆のシーンもホラーである。2019年に邦画は『 貞子 』を送り出し、訳の分からん老婆をガジェットとして配置するだけの一方で、韓国映画界はそのさらに10年前に、ホラー映画ではないのに並みのホラー映画以上に怖い演出を生み出している。いつも間にどうやってこのような差がついたのか。
ポン・ジュノ監督の特徴に中盤で映画の様相がガラッと変わるというものがあるが、同時にこの監督は自らの作品の随所に社会的なメッセージを込めてくるという特徴もある。10年以上前の映画なので同時代的なレビューはできないが、それでもトジュンや母が暮らす街がアーバン・スプロール化現象の先端部にあることは分かる。トジュンの悪友ジンテや廃品回収業者の男の住居などは、その最先端部だろう。まるで『 ボーダーライン 』のとあるメキシコの町のように、無秩序が支配する空間である。殺害された少女アジョンを巡る人間関係の混沌が、居住空間の混沌と不可思議なフラクタルを形成している。ポン・ジュノ監督の社会への透徹した眼差しを、ここに見て取ることができる。
『 ジョーカー 』に通じる(というか、『 ジョーカー 』が受け継いだ)ダンスで始まり、さらにダンスで終わるこのエンディングは、善悪の彼岸を超越した境地に母という存在があることを示しているかのようだ。夕陽に照らされ、踊り狂う数々の黒のシルエットを通じて見えてくるのは、個としての母ではなく、象徴としての母なのか。英語に“Like father, like son.”という諺があるが、“Like mother, like son.”とも言えそうである。母とは、子を産んでこそ母で、トジュンという、これまた善悪の彼岸にあるかのような、ある意味でとても純粋無垢な存在の無邪気さに、我々は怖気を震うのである。母はあの鍼で何を忘れようとし、そして忘れたのか。本作を観る者は、等しくその思考の陥穽に落ちることだろう。何と気持ち悪く、そして心地よい感覚であることか!

ネガティブ・サイド
真相の描写がややアンフェアであると感じた。「あのシーン、実はこうだったんです」と後から言われても、納得しがたい。もっとボカした描写も追求できたのではないだろうか。
ジンテとミナのセックスシーンは眼福だったが、あれは母の位置から見たものだったのだろうか?カメラアングルを母の目線のそれに合わせれば、よりスリリングで背徳感のある絵が取れたと思うのだが。
トジュンの元同級生の刑事が、どこまでもうざったい。最後に「真犯人を捕まえた」と母に報告に来るシーンでも、普通ならもっと神妙になってしかるべきではないか。我が国の警察の人権意識や冤罪への注意の度合いはこんなに低いですよ、というポン・ジュノ監督のメッセージなのかもしれない。だが、シリアスさを増していくばかりの終盤の展開ではノイズのように感じられた。

総評
これは大傑作である。『 パラサイト 半地下の家族 』よりも面白さでは上であると感じる。細部の記憶があいまいになった状態で再鑑賞したことで、ところどころでトジュン的な気分も味わうことができた。ポン・ジュノ監督は、そこまで計算して本作を作り上げたのだろうか。二度目に鑑賞することで、印象がガラリと変わる作品というのは稀にしか巡り合えない。本作は間違いなくその稀な一本である。

Jovian先生のワンポイント韓国語レッスン
チンチャ
本当、の意である。劇中で何度か「チンチャ」と聞こえてきた。日本語と同じように形容詞や副詞として使われているのだろうか。最近の10代の間では「チンチャそれな」というような日韓チャンポンの言葉も使われているらしい。日本も「もったいない」、「カイゼン」に続く言葉の輸出に本腰を入れるべきだ。そのためには韓国に負けないような音楽やダンス、テレビドラマ、映画などのコンテンツを作り、世界に届ける仕組み作りが必要だ。