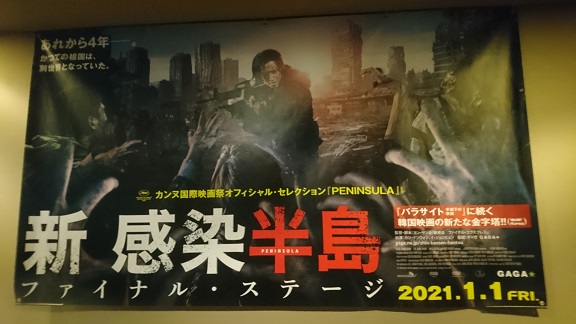ミッション・マンガル 崖っぷちチームの火星打上げ計画 80点
2021年1月9日 MOVIXあまがさきにて鑑賞
出演:アクシャイ・クマール ビディヤ・バラン シャルマン・ジョーシー
監督:ジャガン・シャクティ

昨年2019年夏ごろにNHKの『 地球ドラマチック 』でインドの衛星打ち上げ特集を行っていたのを見て、数学の国がついに天文学にも本腰を入れ出してきたかと感じた。そして本作、インド版『 ドリーム 』がリリース。宇宙開発および映画製作の優等生への仲間入りをさせてもらうぞ、との宣言であるかのようだ。
あらすじ
タラ(ビディヤ・バラン)は過程を切り盛りする主婦であり母であり、そしてISRO(インド移駐研究機関)の職員でもある。ロケット発射の際のほんのわずかな確認ミスのために、打ち上げは失敗。それによりタラと責任者のラケーシュ(アクシャイ・クマール)は閑職の火星探査衛星打ち上げプロジェクトに左遷されてしまうのだが・・・

ポジティブ・サイド
文句なく面白い。その最大の理由は、魅力的なキャラクターにある。実話ベースとはいえ、おそらく登場人物たちは相当にデフォルメされているだろう。けれど、その改変具合が絶妙で、キャラクターの性格や行動がストーリーを違和感なく推し進めていく。映画の冒頭でタラが主婦として母親として奮闘する場面がこれでもかと描写されるが、それがあるからこそ家政・・・ではなく火星到達のための一発逆転のアイデアがタラから出てきたことに納得できるし、そのアイデアの中身に我々はたと膝を打つのである。
敵役のNASA帰りのプロジェクトマネージャーによって指名され、三々五々やって来る経験の浅い女性スタッフたちも個性豊かだ。収納や節約、裁縫など、とても宇宙開発や宇宙探査に関係があるとは思えない分野の知恵がどんどんと現場で生まれ、応用されていく展開が子気味よい。そして、そのアイデアをしっかりと受け止め、吟味し、ゴーサインを出す責任者のアクシャイ・クマールの存在感よ。この役者は『 KESARI ケサリ 21人の勇者たち 』でも、威厳ある上官でありながら、部下が上げてくる声を丹念に聞き取る耳を持っていた。そうしたキャラを演じさせるとハマる。まさにキャリアの円熟期なのだろう。本作で共演する多くの若い女優たちとも過去に共演歴があることも、アクシャイ・クマールをして演技中でもカメラOFFでも、現場をリーダーたらしめていたのかもしれない。
独り者で趣味もないラケーシュが女性たちの献策を容れていくところに、家父長制の色濃いインド社会へのメッセージを感じた。対照的に、妻として母として科学者・技術者としても活躍するタラが、夫や子ども達との距離を模索する姿には複雑な思いを抱かされる。だが、そこに救いもある。これまでのインド映画は、例えば『 シークレット・スーパースター 』や『 あなたの名前を呼べたなら 』のような、女性の耐える姿に美徳を見出すようなものが多かった。しかし本作ではタラは保守的・因習的な夫やイスラム教(いわゆる異教)に改宗する息子、門限を守らない娘たちと理解し、和解し合っていく。「仕事と家庭とどっちが大事なんだ?」という、問うてはいけない質問に、「両方ともに大事だ」という答えを行動で呈示していく。さらに、タラ以外の女性キャラクターたちも呼応。耐えるだけではなく、とある電車内のシーンでは男性モブキャラたちをボコボコにしていく。これは衝撃的だ。『 猟奇的な彼女 』でも、彼女が男性乗客をひっぱたくシーンがあったが、本作はそれを超えている。インドの新時代の幕開けを目の当たりしたように感じる。
探査機の打ち上げ前、そして打ち上げ後も、ベタな手法ではあるが、観客のハラハラドキドキを持続させてくれる。もちろん、歴史的に成功したミッションであることは分かっているが、それでも手に汗握ってしまうのは、それだけ感情移入させられているからだ。『 ドリーム 』のクライマックスでも聞こえてきたが、レーダーコンタクトの瞬間、信号受信の瞬間の安堵のため息が、劇場の数か所から漏れ伝わってきた。
「ハリウッド映画よりも少ない予算で我々は火星までたどり着いた」という演説に思わずニヤリ。予算も大切だが、もっと大切なのは創意工夫である。今後のインドの宇宙開発にエールを送りたくなると共に、インド映画界からエールを送られたように感じた。

ネガティブ・サイド
歌と踊りが少な目である。というか、2シーンしかないし、短い。『 きっと、またあえる 』や『 スラムドッグ$ミリオネア 』のように、エンドクレジットで爆発させてくれるのかと思いきや、それもなし。世界的なマーケットを視野に入れているのは分かるが、インド映画の特徴はやはり絢爛豪華な歌と踊りにあるのだから、そこは忘れてほしくなかった。オペレーション・ルームでサリーを着て踊りまくるMOMの面々を是非とも観たかった。
ラケーシュが歌うキャラクターという点にもう少し一貫性が欲しかった。最終盤に思わず歓喜の歌でも歌うのかと思ったら、それもなし。そこが少し残念だった。
敵役のNASA帰りの鼻持ちならない男が司るプロジェクトの進行状況なども描写されていれば良かった。ミッション・マンガルの面々がそれを知って、奮励したり、あるいは落胆したりといった様子が見られれば、より人間ドラマの要素が生々しくなっただろう。
最後に、映画の中身とは関係ないが、どうしても言いたい。タイトルは普通に『 ミッション・マンガル 』で良いではないか。一体どこの馬の骨が何の権限をもってどういう根拠に基づいて、このようなアホな副題をつけているのか。「崖っぷち」の部分が耳障りだし、「火星打上げ」に至っては完全なる日本語ミスだ。正しくは「火星探査機打ち上げ」または「火星探査機打上げ」だろう。火星という惑星そのものを打ち上げてどうする?誰もこの誤用に気付かなかったというのか?そんな馬鹿な・・・

総評
『 パッドマン 5億人の女性を救った男 』の主演アクシャイ・クマールとその監督のR・バールキが脚本で参加した本作は、インド映画の娯楽性とインド人の問題意識、そして現代インド社会を如実に反映している。サイエンスに関する知識も必要ない。カップルで観ても良し、家族で観ても良しの秀作である。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
Those were the days.
「あの頃が懐かしい」の意。
Those were the days. There was no such thing as consumption tax.
あの頃は良かったなあ。消費税なんか無かったし。
Those were the days. Hardly anybody wore a mask.
あの頃が懐かしい。マスクを着けている人なんかほとんどいなかった。
自分バージョンを色々と英作文してみよう。