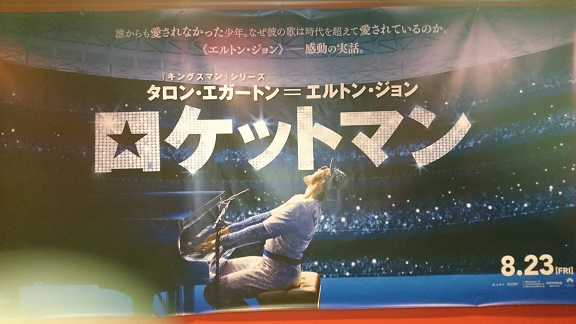メアリーの総て 65点
2019年10月26日 レンタルDVDにて鑑賞
出演:エル・ファニング ダグラス・ブース ベル・パウリー
監督:ハイファ・アル=マンスール

フランケンシュタインの怪物の影響は現代まで連綿と続いている。日本では漫画『 ドラゴンボール 』の人造人間8号などは好個の一例だろう。けれども、そのキャラクターと物語を生み出した作家メアリー・シェリーについてはそれほど知られていない。だが、今という時代に彼女の映画が作られたことには必然性があったのだ。
あらすじ
19世紀のロンドン。書店の娘メアリー(エル・ファニング)は物書きになることを夢見て、様々な本を渉猟していた。ある日、妻子のあるパーシー(ダグラス・ブース)と恋に落ちたメアリーは、彼と駆け落ちする。それは、彼女の波乱万丈の人生の始まりだった・・・
ポジティブ・サイド
現代物でも歴史物でも、ロンドンという都市には陰鬱な雰囲気がある。それは本作でも巧みに表現されている。街の空気が重苦しく感じられ、母親などから仕事を手伝うようにプレッシャーをかけられても、メアリーは快活さを失わない。彼女は自身の内に響く言葉を解き放つことを恐れない。『 未来を花束にして 』の二世代前の時代、女性が自分らしく生きることは想像を絶するほどに困難だったと思われる。だからこそ、メアリーのキャラクターが立つし、観る者はメアリーを応援したくなる。エル・ファニングは少女と女性の中間のような存在を好演してくれた。ラブシーンもちょこっとあるので、スケベ映画ファンはほんの少しだけ期待してよい。
異形の、しかし心優しい怪物を構想し、執筆する背景になにがあったのか。メアリーは16歳という若さで情熱に身を任せ、妻子ある男と駆け落ちしたが、そんなものは誰がどう見ても幸せにはつながらない。現代の目で見てもそうだし、家族や当時の人々もそう思っていたことだろう。弱冠18歳にして「フランケンシュタインの怪物」を生み出した彼女は、そのエンディングに関して、パーシーからアドバイスを得る。しかし、それを採用しない。なぜなら、それこそが彼女の心だから。なぜなら、その作品が彼女の子どもだから。ボリス・カーロフ主演の『 フランケンシュタイン 』で、怪物が少女と湖畔で遊び、語らうシーン、そして怪物が武器を手にした村人たちに追われるシーンが思い起こされた。少女が誰を象徴しているのか、村人たちが誰を象徴しているのかに、しばし思いを巡らせてみるのも一興だろう。
美とは何か。創作とは何か。メアリー・シェリーの10代を通じて、色々なものが見えてくるし、考えさせられもする。
脇を固めるダグラス・ブースは見事なクズ男を演じた。パーティーで詩文を恭しく詠んでは、先進的な思想をひけらかして女性を引っかけていくという典型的なプレイボーイで、加えて生活力や金銭管理能力にも劣る。そんなすきに慣れそうにないキャラクターを見事に好演。日本でいえば、一頃の藤原竜也だろうか。『 マイ・プレシャス・リスト 』でタイトル・ロールのキャリー・ピルビーを演じたベル・パウリーも印象的。「詩人に気に入られる女性はあなただけじゃない」とメアリーに言ってのけるシーンに、女性という生き物のプライドを垣間見たように思う。
ネガティブ・サイド
ストーリーのペーシングに難がある。メアリーという女性がいかにしてフランケンシュタインの怪物を構想し、執筆したのかという場面までなかなかたどり着かない。監督や脚本家に、「メアリーという人間を掘り下げて描き出したい」という願望が強すぎたように思う。その割には、彼女が赤ん坊を早くに亡くしてしまったことの負い目が、それ程強調されていなかった。怪物は二重の意味でメアリーの子ども(血を分けた我が子が復活した姿と創作物)なのであるから、子に先立たれた親の悲嘆について、もう少し詳細な描写や演出が欲しかった。
メアリーとポリドリ医師の距離感というか、この二人がもっと熱心に生や死について語らう場面があってもよかったはず。当時の英国の死生観や科学観をもう少し丁寧に劇中で描けていれば、メアリーが創作のためにどのようなインスピレーションを得たのかを我々としては想像しやすくなる。
総評
近代ホラーおよびSF文学史に興味がある向きならば必見だろう。現代は過去の様々な作品が脱・構築され、フェミニスト・セオリーが適用され、再生産されている時代である。女性作家としてはジェーン・オースティンと並ぶ、まさに元祖である。彼女のbiopicを見ずして、現代の映画製作のコンテクストは語れない・・・は、さすがに言い過ぎか。エル・ファニングのファンならば鑑賞必須である。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
speak ill of ~
~の悪口を言う、~を悪しざまに言うの意である。序盤でメアリーが「私の母を悪く言わないで」というシーンがある。反対の意味の表現として、speak highly of ~がある。~を褒める、の意である。こちらも序盤にパーシーがメアリーの家にやって来る時に使われていた。TOEICにはまず出てこないが、英検やTOEFLには偶に出てくるかもしれない。