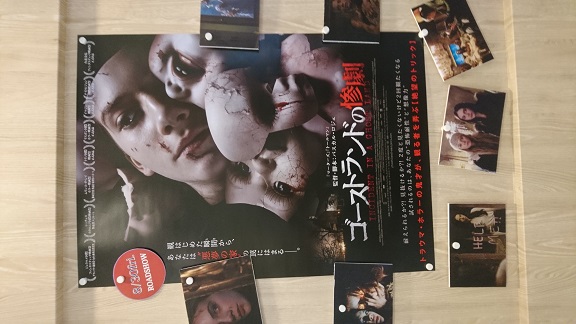ゴースト・ストーリーズ 英国幽霊奇談 60点
2019年11月12日 レンタルDVDにて鑑賞
出演:マーティン・フリーマン アンディ・ナイマン
監督:ジェレミー・ダイソン アンディ・ナイマン

シネ・リーブル梅田でタイミングが合わず見逃してしまった作品。海外のレビューでは結構評判がよかったので、TSUTAYAで借りてきた。ジャンプスケアばかりのアメリカのホラー映画とは異なり、人間の心の分け入っていくところが英国流か。
あらすじ
心理学者のグッドマン(アンデイ・ナイマン)はインチキ霊能者の嘘やイカサマを暴いてきた。だがある時、彼の憧れの存在であり、疾走していたキャメロン博士よりコンタクトを受ける。曰く、「この3つのケースは説明が付けられない」と。グッドマンは3人それぞれのインタビューに向かうが、彼はそこで不可思議な体験をすることになり・・・
ポジティブ・サイド
久しぶりにまともな副題が付されている。“英国幽霊奇談”とはなかなかに洒落ている。もっともこうでもしないと『 A GHOST STORY ゴースト・ストーリー 』と区別がつけにくくなるという事情もあるのだろうが。
大きな音や視覚的に不穏な表現を使うことで怖がらせよう、いや、驚かせようとするシーンが少ない。これは良いことである。恐怖とは受動的に感じさせられるものと、能動的に感じてしまうものとがある。本作が追求しようとしているのは後者である。これは一体なんなのか。何が起きたのか。どのように起きたのか。何物がそれを引き起こしたのか。何故それが引き起こされたのか。こうした次々に湧いてくる問いに、答えを示唆するものもあれば、完全に受け手の想像力に委ねてくるものもある。その塩梅がちょうどよい。そして、その塩梅の良さがそのまま結末への伏線になっている。ジェレミー・ダイソンとアンディ・ナイマンの二人はかなりの手練れである。
「脳は見たいものを見る」というのは、定期的に話題になる。Jovianがよく覚えているのはこの画像である。コロッと騙された覚えのある男性諸氏も多かろう。本作の投げかけるテーマは、この画像のようだと思ってよい。見えないものは見えないし、見えたとしてもそんなものは子供騙しだと退ける。人間の心理とは斯くのごとしである。これを言ってのけるのが心理学者であるというところが味わい深い。また、心理学に造詣の深い向きならば「行為者-観察者バイアス」を念頭に本作を鑑賞するとよいだろう。
ネガティブ・サイド
この結末は賛否両論を呼んだことだろう。Jovianは否である。それは恐怖の余韻をぬぐい去ってしまうからではなく、恐怖の根源が説明できてしまうからである。ネタばれになるので何も書くことができないが、この結末は「脳は見たいものを見る」ということの恐ろしさを伝えるものではない。いや、伝えてくれてはいるものの、この手の結末は小説などで散々使いまわされてきた。ここをもう一捻りするか、あるいは結末部分の3分間をデリーとすることも考慮するべきだったように思う。
3つのケースの怪異の描き方にも改善の余地がある。特に2人目のケースでは、「木」はパートは無用である。というよりも、これで恐怖感を煽るとするならば島田荘司の小説『 暗闇坂の人喰いの木 』以上のおどろおどろしさを演出する必要がある。このあたりに英国の幽霊譚の限界があるように感じた。もちろん、比較文化論的な意味であって、絶対的にそうであるというわけではない。Jovian一個人の感想である。
総評
もっと面白く作れたのではないかと思えてしまうのは文化の違いだろうか。ただし、ジェームズ・ワンの手掛ける虚仮脅し満載のギャグと紙一重のホラー映画とは異なり、人間の心理の単純さと複雑さ、そこを探索しようとしたことには一定の意義が認められるだろう。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
Certainly not.
「生き物を殺したことはあるか?」と問われたグッドマン教授の返答である。“No.”の一言ではぶっきらぼうである(口調や表情にもよるが)。“Certainly not.”というのは、かなり丁重な表現である。類似の表現をフォーマルからカジュアルに並べると
Certainly not. > Definitely not. > Absolutely not.
となる。これは肯定形にしても、つまりnotを取り除いても同じである。ビジネス・シチュエーションで顧客や上席に返事をするときは“Certainly.”や“Certainly not.”を使うようにすべし。