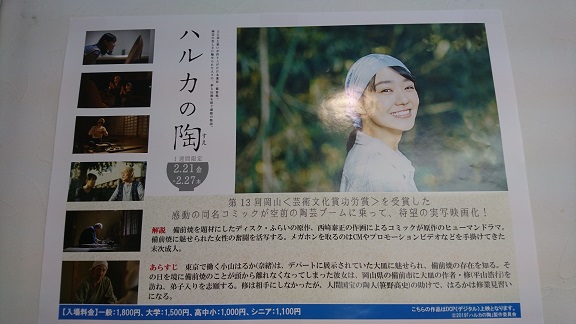37セカンズ 80点
2020年2月9日 MOVIXあまがさきにて鑑賞
出演:佳山明 神野三鈴 大東駿介 渡辺真起子 板谷由夏
監督:HIKARI

日本に格差が根付いて久しい。その一方で、コンビニの店員さんがノン・ジャパニーズでいっぱいになったり、あるいはあちこちの中規模駅にエレベーターが設置され、車イスの乗客を見ることが日常的になったりと、日本社会は確実に包括的な方向にも向かっている。そうした中、障がい者に焦点を当てた映画に、また一つ傑作が生まれた。
あらすじ
23歳の貴田ユマ(佳山明)は脳性まひのため、手足の運動が思うようにならない。しかし、絵を描く才能に恵まれていたユマは、売れっ子漫画家のアシスタント(実際はゴーストライター)をして生計を立てていた。そんなユマを母(神野三鈴)は過保護に育てていた。自立を求めるユマはアダルト誌に原稿を持ち込むが「性体験がないとリアルな作品は描けない」と言われてしまう。夜の歓楽街、風俗街に入り込んだユマは、そこで舞(渡辺真起子)や俊哉(大東駿介)らと知り合い、新しい世界を知るようになる・・・

ポジティブ・サイド
車イス、あるいは重度の障がい者が主人公や主要キャストの映画となると、
『 ドント・ウォーリー 』
『 パーフェクトワールド 君といる奇跡 』
『 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 』
『 ブレス しあわせの呼吸 』
『 最強のふたり 』
『 パーフェクト・レボリューション 』
『 博士と彼女のセオリー 』
などがパッと思い浮かぶ(一部、クソ作品が混じっているが思いついた順に列挙しているだけなので気にしないでほしい)。それぞれにテーマがあり味わい深い作品であるが、この『 37セカンズ 』が特に優れている点は二つある。一つには、主演を務めた佳山明の演技と、それを引き出した監督の力量。もう一つには、障がい者ということそのものをテーマの主軸にしていないことである。
演技のバックグラウンドのない主役を、経験豊富な役者たちがカバーすることで生まれる一体感というのは確かにある。毎回ではないが、時々素晴らしいケミストリーを起こす。最近では『 町田くんの世界 』の主役二人にそれを感じたし、『 風の電話 』からも感じ取れた。それでは本作の主役である佳山明が実力ある脇役に支えられながら、町田君やハル以上に輝くのは何故なのか。彼女自身が脳性まひを患った本当の身体障がい者であるということが指摘できる。それにより演技が演技に見えないのである。というか、演技なのに演技ではないのである。映画というのは一部のジャンルや作風を除けば虚構の芸術である。『 ボヘミアン・ラプソディ 』は伝記映画であったが、現役の歌手にフレディを演じさせるという選択肢も、制作前には検討されたはずである。役者に歌わせるよりも、歌手に演技させた方が良いという場合もある(ちなみに、これで大失敗したのが『 タイヨウのうた 』)。実力ある俳優に障がい者を演じてもらうよりも、障がい者が物語世界に降臨した方が説得力がある。これはそうした作品であり、さらにそれを成功させている。冒頭の入浴介助のシーンでは佳山も神野もヌードを披露してくれる。Jovianはこれで一気に本作をドキュメンタリー映画であると受け止めてしまった。すべてが計算ずくで作られたドラマではなく、現実を忠実に映し取った作品であると感じたのだ。このような導入でリアリティを生み出すとは、HIKARI監督は手練手管を心得ている。障がい者が障がい者を演じるのは演技と言えるのかと思う人もいるかもしれない。だが、こう考えてみてはどうだろう。邦画お得意の実写青春映画で美少女が美少女を演じることはどうなのか。イケメンがイケメンを演じるでもいい。橋本環奈が不細工な女子高生という設定や、松坂桃李が醜男という設定に納得できる人がいるだろうか。本作での佳山のキャスティングにケチをつける人は、一度自分の思考を整理されたし。それがすなわち差別であるとまでは言わないが、障がい者を特別視している自分がいることに気づくことだろう。
本作で佳山が特に光っているのは、人懐っこい笑顔を見せる時である。上で書いたことと少々矛盾して聞こえるかもしれないが、人が人を魅力的に思うのは見目麗しさ以上に、笑顔であると思われる。ユマの笑顔を見よ。これほどチャーミングな笑顔が邦画の世界でどれほど映し出されてきただろうか。そう思えてくるほどに、ユマの笑顔には魅力がある。人間関係の基本にして究極がそこにある。目の前の人を笑顔にすること。それに必要なのは、介護の知識やスキル、ポリコレ意識ではなく、対等な人間関係を結ぶということなのだろう。
本作は障がいそのものをテーマとはしていない。障がい者であるユマが恋愛やセックスに興味を持つのは年齢的にも肉体的にも自然なことである。似たようなところでは『 聖の青春 』の村山聖が挙げられる。もしくは『 覚悟はいいかそこの女子。 』の恋愛未経験イケメン男子を思い起こしてもいいだろう。恋愛やセックスは健常者だと障がい者、イケメンだとかブサメンだとかは関係ない、普遍的なテーマなのである。本作のユマがユニークなのは恋愛やセックスへの興味以上に、自分の仕事の幅を広げたい、あるいは深みを増したい、自立をしたいという強い想いに駆られている点である。恋愛やセックスそれ自体がゴールになっていることが多い日本の多くのエンタメ作品とは、そこが決定的に異なっている。『 娼年 』をカネで買ってスムーズに初セックス・・・とならない。このあたりから物語が一気に加速していく。舞や俊哉と共に生き生きと過ごすユマに、我々は逆説的に教わる。すなわち、恋愛やセックスはそれ自体が単独で成立するイベントではなく、濃密なコミュニケーションや人間関係の一側面である、と。そして、ユマに対等に接してくれるのは夜の街のポン引きだったり、クィアな方々であったり、ゲイバーの店員と思しき人々だったりする。社会のはみ出し者、日陰者とされているような人々なのだ。だが、彼ら彼女らの交流の模様がスクリーンを鮮やかに彩るのを見れば、「障がいも個性の一つ」という少々行き過ぎた考えにも頷けるような気がしてくる。ユマが不意に宇宙人を夢想するのは、宇宙人から見れば、地球人はすべて地球人という同じカテゴリに分類されるからだろう。そこにはもはや人間関係の上下や思考の左右の違いはない。本作は障がい者ではなく人間を映し出している、言葉そのままの意味でのヒューマンドラマなのだ。
ユマの自立への旅は思わぬ方面にまで飛んでいくことになるが、そこはぜひ劇場で鑑賞を。彼女が家に帰って来るシーンでの母親の落涙は、完璧に計算された証明とカメラアングル、そして演技によって成立している。ここには作為を感じたが、その美しさに観る者の胸はいっぱいになることだろう。
映画的な文法に忠実に従って、すなわち映像で物語を語らせる場面が多いのも良い。未見の方は、ユマが這ってシャワーを浴びに行くシーンで、彼女の両足に土踏まずが全くないことを見逃さないようにしよう。そのうえで、母親が見つめるとあるアイテムが何なのかをじっくり考えるようにしよう。その先には非常に上質な人間ドラマが待っている。

ネガティブ・サイド
大東駿介演じる介護士はいったい何者なのだ?片言ではあるが、英語や、その他外国語を操れるのは何故だ?組織に属する介護士ではなく、フリーランス・自営業的に介護サービスを提供しているのか?いや、それでは自分が風邪を引いただけで代わりを見つけることもできず、顧客に迷惑をかけるだけだ。この男はいったい・・・
またユマがパスポートをしっかりと持っているのは何故だ。所有しているだけなら構わないが、あのタイミングで持っていることは不可解極まりない。運転免許証以外の身分証明書。ということなら普通に障がい者手帳で間に合うはずである。終盤入り口の超展開には少々納得がいかなかった。
アダルト誌編集長を演じた板谷由夏の「セックスをしたことがないとリアルな作品を描けない」というのは一理あるが、別にセックス経験がなくとも面白い作品は描けるはずだ。「人を殺したことがないのに、面白い殺人事件は書けないだろう」などと言う編集者がいたら「頭がおかしいのか?」と思うだろう。

総評
エンドクレジットになぜか我が町・尼崎の尼崎市立身体障害者福祉センターが出てきてびっくりした。何か縁があったのだろう。分断をキーワードにする映画が続々と生産されるなか、“包括”や“包含”をテーマにする作品も同じくらい作られていいはずだ。本作を観れば、世界が目指すべきは分断ではなく包括であることは自ずから明らかである。とにかく、できるだけ多くの老若男女に観てもらいたいと思える傑作である。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
get laid
セックスする、の意である。直訳のhave sex でも良いが、日常会話ではget laidをよく使う気がする。面白いことに、この表現では相手を表現することは滅多にない。他に同様の意味の表現としては
have sex with somebody
sleep with somebody
make love to somebody
hook up with somebody
などがある。こういう表現が実地に使えるようになれば、英会話スクールは卒業してよい。