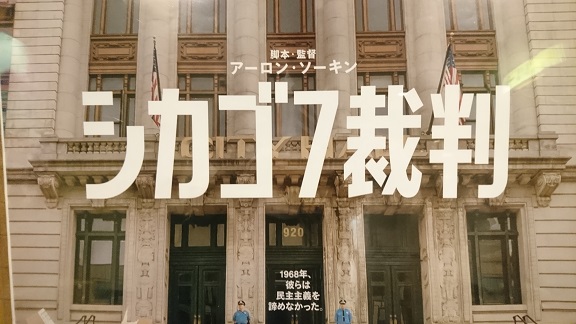シャッフル 50点
2021年2月4日 レンタルDVDにて鑑賞
出演:サンドラ・ブロック
監督:メナン・ヤポ

緊急事態宣言以後、嫁から尼崎市内から極力出るなとのお達しが出ている。本当は梅田や心斎橋に足を伸ばしたいのだが・・・。一方で映画を観る人は増えているようだ。事実、近所のTSUTAYAは明らかに客が増えている。配信ではなくレンタルというところに日本のデジタル化の遅れを実感するが、それでもVHSからDVD、Blu-rayのカバーボックスの表と裏でキービジュアルやプロットをチェックするのは楽しい。本作もタイトルとカバーのデザインだけでレンタルを決めた。
あらすじ
リンダ(サンドラ・ブロック)のもとに保安官が訪れ、夫のジムが交通事故で死亡したと告げる。呆然自失するリンダは翌日、出勤前にリビングでくつろぐ夫と出会う。だが、さらにその翌日、ジムは亡くなっていた。時間の流れがシャッフルされているのか。リンダはジムを救うことができるのか・・・
ポジティブ・サイド
高畑京一郎の小説『 タイム・リープ―あしたはきのう 』を映像化すると、このような作品になるのだろう。タイムトラベルやタイムスリップは、それこそ星の数ほど小説でも映画でも使われてきたが、時間をバラバラに経験するというのは珍しい。時間の描写を逆にするのは『 メメント 』などもあり、珍しいものではなくなってきているが、本作のように時間の順序をシャッフルしてしまうというアイデアは秀逸だと思う。このことによって思わぬサスペンスが生まれている。
例えば娘の顔の傷。あるいは洗面所に無造作に放置された錠剤。謎が生まれるたびに、その謎がいつの時点で発生したのかを考えてしまい、引き込まれる。これが例えば『 オフロでGO!!!!! タイムマシンはジェット式 』のような普通のタイムトラベルものだと、現代と過去の違い(たとえば片方の腕の有無)から、過去に何かが起きたと分かる。問題は、時間の流れが一方通行であるため、現代につながる事件の起きる瞬間に対して主人公たちが受け身にならざるを得なかったところ。本作は逆に、待っていれば欲しい情報が得られるわけではない。次から次へと意味不明の展開が起こり、別の曜日になってみて初めて、その意味が分かる。ある意味で『 TENET テネット 』のような構成なのだ。ここが非常に新鮮で面白かった。
オチも、この手の時間改変スリラーの中では王道と言えるものだが、後味は悪くない。むしろ、Memento moriの元来の意味に近いCarpe diemという哲学を想起させる。Milfyなサンドラ・ブロックが堪能できる佳作。
ネガティブ・サイド
超常現象、あるいは怪奇現象を思わせる演出のすべてがノイズである。カラスの死骸のシーンでは、「あれ、これって『 ペイ・ザ・ゴースト ハロウィンの生贄 』の系統のストーリーなの?」と感じてしまった。妙な演出など不要、ストレートに不可解なシャッフル現象だけを取り上げれば良い。ストーリーの根本にあるのは「何故こうなっているのか」ではなく、「この状況で何をなすべきか」なのだから。
ジムの出棺のシーンもめちゃくちゃ。『 ドクター・デスの遺産 BLACK FILE 』でも、御棺を警察官2人で軽々と運ぶシーンがあったが、プロレスラー並みの力持ちかいな。本作は本作で、男二人で運ぼうとした棺をガタンと落としてしまい、中から首がゴロゴロゴロ、ってそんな馬鹿な。普通は簡単にでも縫い合わせる。その上で縫合部に包帯を巻くのが常道だ。ここでも場に不穏な空気を流したいという園主のためだけに、リアリティが著しく損なわれてしまっている。なんでもかんでも現実に即せと言いたいわけではない、念のため。その作品の持つ世界観と合っていないのだ。
世界観にマッチしない最大のノイズと感じたのは、牧師?神父?がリンダに教えを与えるシーン。信仰の本質を突いた鋭い説教だと感じたが、これを最終盤手前に持ってくるのなら、序盤のホラー的な演出はすべてが無意味である。なので、このシーンをバッサリ削るか、あるいはこけおどしシーンを全て切り落として説教のシーンを活かすかである。監督:メナン・ヤポ監督は、このあたりのバランスを見失った。二兎を追う者は一兎をも得ずである。
総評
壮大な謎や陰謀の存在をにおわせるが、その謎解きも無し。けれども『 エミリー・ローズ 』のように謎を解くことに主眼があるのではなく、その謎に立ち向かう人間の姿に美点を見出すならば、なかなかの良作と言えるのではないだろうか。英語でたまにa rainy day DVD=雨の日にちょうど良いDVDと言ったりするが、時代に合わせてa stay-home day DVD=外出自粛日にちょうど良いDVDという言葉を提唱したい。本作は、a stay-home day DVDである。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
Tell me about it.
『 やっぱり契約破棄していいですか!? 』でも紹介したフレーズ。「言われなくても分かってるさ」、「まったくその通りだ」、「よく分かるよ」という意味である。こうした表現をナチュラルに使えるようになれば、上級者の一歩手前である。