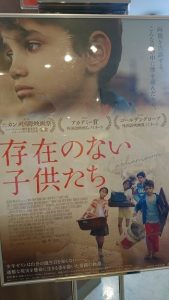エンテベ空港の7日間 55点
2019年10月13日 レンタルDVDにて鑑賞
出演:ダニエル・ブリュール ロザムンド・パイク
監督:ジョゼ・パジーリャ

嫁さんの希望で台風明けに本作を鑑賞。我が家はたいていの場合、婦唱夫随なのである。Jovianもトレイラーなどから少し興味を持っていた。だが、『 アルゴ 』のような水準を期待してはいなかった。結果的に、それで正解であった。
あらすじ
1976年。ボーゼ(ダニエル・ブリュール)とクールマン(ロザムンド・パイク)はエールフランス機をハイジャックし、ウガンダのエンテベ空港に飛行機を降ろす。彼らの狙いは獄中のパレスチナ解放闘士の解放。イスラエルのラビン首相と国防相のペレスは態度を保留しつつ、交渉と軍事作戦の両方を立案して・・・
ポジティブ・サイド
ハイジャック、というよりもテロリストという呼称の方がふさわしいか。我々はテロリストという人種には血も涙もないと考えがちである。事実、『 ホテル・ムンバイ 』が描き出すテロリストたちには血も涙もなかった、中盤までは。実際に彼ら彼女らも生きた人間であり、人間であるからには親から生まれ、生まれたからには最初の数年から十数年は誰かに育てられたはずなのだ。そこで洗脳されてしまえば終わりであるが、人と触れ合わずに生きることは不可能である。テロリストにも人間らしさがあるという視点は、当たり前ではあるが新鮮でもあった。本作は、そのテロリストを主人公に据える。『 シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ 』や『 ユダヤ人を救った動物園 〜アントニーナが愛した命〜 』などの作品と同様に、ダニエル・ブリュールは善悪の境界線上を行くようなキャラクターを演じさせれば、非常に良い仕事をする。ロザムンド・パイクも『 プライベート・ウォー 』とは全く逆のキャラクターを見せかけて、本質的には同じような人間を演じている。すなわち、自分の生命よりも自分の信念に忠実なタイプの人間だ。そうであっても、例えばパイクのキャラクターも飛行機の乗客から、「シャツのボタンが一つ外れている」と指摘され、思わず女性性を発露させてしまうところや、ブリュールのキャラにしても、妊娠していると言う女性を解放したりと、人間性が感じられた。
特に、ブリュールのキャラに関しては、エンテベに向かう前の給油地での機関士との会話、そしてエンテベに着いて以降の機関士との会話で、自分自身の正義の定義が揺らいでいるように感じた。というよりも、元々、善悪の狭間にいるのではなく、自らの信念と思考の中間点に囚われやすい人物なのかもしれない。自分はドイツ人だが、ナチではないという主張もこのことを裏付けているように思う。本人に取材できたはずはないので、このあたりがジョゼ・パジーリャ監督の構想及び解釈なのだろう。
テロリスト同士の対話、テロリストと人質の対話でストーリーが進行していく中、イスラエルのラビン首相とペレス国防相の駆け引きも大いなるスリルとサスペンスを生んでいる。事態の解決に向けてのアプローチがそのまま彼らの水面下での駆け引き、権力闘争になっているところが興味深い。またラビン首相の指摘、すなわち「パレスチナは敵だが、隣国でもある。彼らから離れることはできない。いつか話し合いで和平をもたらす必要がある」という言葉がそれだ。アメリカには厄介な隣国として、例えば『 ボーダーライン 』で描かれるようなメキシコがあり、インドには『 バジュランギおじさんと、小さな迷子 』で描かれたようなパキスタンという隣国がある。日本には北朝鮮および韓国という、なかなか手強い隣国があるが、れいわ新選組の山本太郎も「国の位置は動かせない」と冷静に指摘している。本作はアクションの少ない対話劇である。大人の対話をじっくりと鑑賞しようではないか。

ネガティブ・サイド
対話劇であることは良いが、最後の最後に見せ場であるはずのオペレーション・サンダーボルトが、本当にサンダーボルトの如く、一瞬で終わってしまう。せっかく劇場の大画面と大音響で映画を鑑賞するのだから、もう少し見せ場を作って欲しかった。
オープニングから随所に挿入されるダンスも蛇足である。バタンと倒れ続ける1人は、例え一部に脱落者がいたとしても、「”The Show Must Go On” ですよ」と言いたいのだと思うが、それならエンディングのクレジットシーンに舞台ダンスシーンの全てを持って来ても良かった。ダンスシーンが各所に入れられることで、ただでさえ歩みの遅い物語のペースが更に悪くなっていたように感じた。
配球会社や広報会社は盛んに「4度目には訳がある!」と、古い革袋に新しい酒が入っているかのように喧伝していたが、テロリストの苦悩や葛藤、その悲劇性ならば前述した『 ホテル・ムンバイ 』の方が遥かに生々しかったし、思考と信念の違いに思い至り愕然とする人物の描写ならば『 判決、ふたつの希望 』が先んじているし、完成度でも優っている。
総評
イスラエルとパレスチナの問題は、もう百年以上続いている。何がどうしてこうなったのかは一言で説明できないが、欧米列強、就中、イギリスが元凶であることは間違いない。しかし、そうしたことはおくびにも出さず、テロリストの葛藤に焦点を当てた対話劇を作り上げたのだと思えば、パジーリャ監督への評価も上がることはないが、下がることもない。政治的ドラマではなくヒューマンドラマを観るつもりでチケットを買われたし。
Jovian先生のワンポイント独語会話レッスン
Scheiße!
劇中でロザムンドが吐き捨てるドイツ語の卑罵語である「シャイセ!」と発音しよう。英語では“Shit!”となる。排泄物を指して苛立ちを表現するのは、どこの国でも変わらない。Jovianの大学の先輩にドイツ留学者がいたが、彼も常に「シャイセ!」と吐き捨てていた。