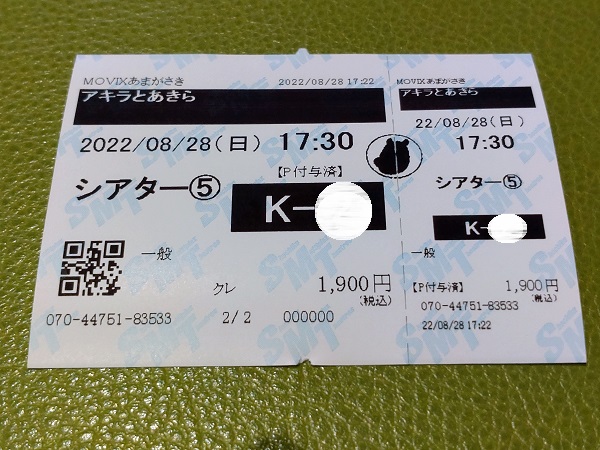レインマン 85点
2022年9月14日 大阪ステーションシティシネマにて鑑賞
出演:ダスティン・ホフマン トム・クルーズ
監督:バリー・レビンソン
『 テルマ&ルイーズ 』と同じく、午前十時の映画祭にて鑑賞。同じくロードトリップの傑作。

あらすじ
チャーリー(トム・クルーズ)は、義絶していた父が死んだと聞き、遺産目当てに葬式へと向かった。しかし、300万ドルの遺産は管財人を通じて特定の人物に相続されることに。その人物が、存在すら知らなかった自閉症の兄レイモンド(ダスティン・ホフマン)だと知ったチャーリーは、遺産の半分の相続を法的に主張するために、レイモンドをLAへ連れていこうとするが・・・

ポジティブ・サイド
『 トップガン マーヴェリック 』では年齢を感じさせなかったトム・クルーズだが、本作では流石に若々しさに満ち溢れている(当たり前だ)。同時に、ビジネスも上手くなく、同僚の操縦も下手で、ガールフレンドへの当たりも強い。つまりはクズなわけだが、そんな男が遺産目当てで出向いた父の葬式で、実は兄がいて、しかもその兄がまともなコミュニケーションを取ることができない自閉症の兄との旅路で思いがけない挫折と成長を味わう。
こう書くと実にありきたりなプロットというか、純文学の香りすらしてくる。しかし、中身は実にまっとうなエンターテイメントで、いかにもアメリカといった趣のあるヒューマンドラマにしてロードトリップ・ムービーである。
イライラして怒鳴り散らすトム・クルーズには若気の無分別という言葉がピッタリ。母は幼くして亡くなり、少年時代に父親に愛情を注がれなかったと固く信じている、まさに愛情不足の典型のような青年だ。そんな男がカネ目当てに自閉症の兄を施設外に無断で連れ出すのだから、応援できるわけがない。しかし、そんなチャーリーを期せずして変えてしまうのが、兄レイモンドである。
ダスティン・ホフマンの演技はキレッキレで、ALSなら『 博士と彼女のセオリー 』のエディ・レッドメイン、自閉症なら本作のダスティン・ホフマンを超える演技は不可能だと思わされた。
コミュニケーションが成り立っていない状態で延々と話し続けるシーンや、クルマが走りながら話すシーンが非常に多く、どれだけのNGあるいはリテイクがあったのか気になる。前編これ、トム・クルーズとダスティン・ホフマンの演技合戦である。特にホテルの一室で二人がダンスするシーン、そして期せずして二人の距離が大きく変化する瞬間ほど poignant なものは、近年の映画では思いつかなかった。
レインマンというタイトルの意味が明らかになる中盤からは至高のヒューマンドラマとなる。旅は人を変える。月並みな真実だが、それを非常に説得力のある形で提示した傑作である。
ネガティブ・サイド
一点だけ不満なのが、なぜレイモンドがあれほど心理的にスムーズに施設の外に出られたのかということ。なにか一つだけでも、「この男は、幼かったあの子が成長した姿だ」と彼なりに感じ取る契機というか、ほんのちょっとした気付きのエピソードがあればパーフェクトだったと感じる。
総評
文句なしの大傑作。ロードトリップものとしては『 テルマ&ルイーズ 』に勝るとも劣らない。障がい者(ということ語弊があるが)をメインに据えた作品としては『 フォレスト・ガンプ/一期一会 』よりも上だと感じる。若いトム・クルーズが粗削りな演技ながらも、盟友ダスティン・ホフマンに食らいついていく様を見ると、『 トップガン マーヴェリック 』の撮影開始前に、彼が若い俳優たちに彼自身が考案した3か月の特別訓練を課したというプロフェッショナリズムの原点はここにあったのかもしれない、とすら思える。stand the test of time forever な作品である。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
take over
引き継ぐの意。遺産ではなく、事業や業務を引き継ぐ時に使う。劇中では “I’ll take over from here.” = ここからは私が引き継ごう、となっていた。もちろん、I’ll take over your job. = 僕が君の仕事を引き継ぐよ、のように目的語を取ってもいい。我が業界では、割と頻繁に非常勤講師が代わるので、テイクオーバーはもはや日本語と化している。嘆かわしい限りである。