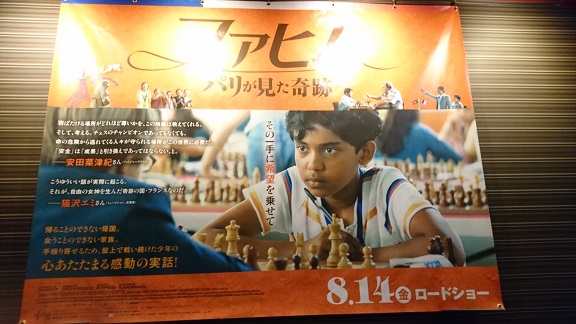喜劇 愛妻物語 70点
2020年9月12日 MOVIXあまがさきにて鑑賞
出演:水川あさみ 濱田岳
監督:足立紳

『 志乃ちゃんは自分の名前が言えない 』の脚本家、足立紳が原作・脚本・監督を手掛けた一作。喜劇と銘打っている割には笑えないシーンも多かったが、大筋では世の既婚男性を既婚女性の両方をエンターテインできる作品に仕上がっている。
あらすじ
売れない脚本家の豪太(濱田岳)は、超恐妻のチカにまったく頭が上がらず、夫婦の営みもほとんどなし。ある時、豪太の脚本家が映画になりそうだということで、豪太は妻チカと娘アキを連れて香川まで取材旅行に出向く。そして、これを機に妻とセックスしようと決意するのだが・・・

ポジティブ・サイド
冒頭の川の字で寝ている親子の朝のシーン。娘が居間でテレビを観始めたところで、妻の方ににじり寄る豪太の何と情けない姿であることか。妻の体を触るのに、それほどおどおどしてどうする。堂々と触れ!お前は俺か!!そのように心の中で叫んだ日本の恐妻家たちの数はいかほどだろうか。試算では軽く200万人はいると思うのだが、どうだろう。
上手いなと感じたのは、夫・豪太の年収を50万円に設定したところ。男はアホな生き物なので、何か一つ相手に勝っているものがあれば安心できる。それが収入なら尚更である。チカ=水川あさみ級の美女を嫁に持つことができる男など、日本では1万人もいるかどうか。その点で、この映画を観る男性のほとんどは豪太に嫉妬する。嫉妬せざるを得ない。水川あさみと代わりに同衾させろ。そこで脚本家の足立紳は言葉の暴力を妻チカに振るわせ、豪太に浴びせかける。妻に虐げられる全国200万人の同志は、チカの言葉の暴力の容赦の無さに怖気を震うことだろう。そして自分の妻を思い浮かべて「本質的にはウチもアッチも変わらねーな」と感じる。何故そのように感じてしまうのか、その絶妙な仕掛けを知りたい人はぜひ観るべし(ただし独身者および未成年は除く)。
チカと、その親友のユミ(夏帆)の女子会的な夜のトークも軽妙にして重厚だ。野郎同士は夜に集まって話しても仕事絡みの愚痴か、浅薄な政治経済論ぐらいである。つまり自分がない。空っぽだ。対して女子には自分がある。自分の感覚を何よりも信じているし、大切にしている。そこにはとてもユーモラスで、なおかつ恐ろしい男女のコントラストがある。ユミの行動原理と豪太の行動原理を比較対照してみると実に面白い。
クライマックスは圧巻である。ラブホテル、川、道路、墓場で親子が三位一体となる姿はカオスの極致である。ラブホ=恋愛、川=三途の川、道路=境界線、墓場=人生の終着点のシンボルだと思えば、結婚、夫婦、家族という関係が人それぞれにくっきりと浮かび上がってくることだろう。
エンディングも味わい深い。豪太の目線の先にあるもの、それは妻の愛だった。『 青い鳥 』のように、幸せは常にそこにあった。結局、男とは女に支えられないと一人立ちできない哀れで未熟で、それゆえに愛おしい存在なのかもしれない。
ネガティブ・サイド
それにしても豪太の情けなさよ。妻とセックスしたくてたまらないのは分かるが、やり方がいちいち姑息なのだ。もちろん、その過程を楽しむ作品なのであるが、豪太の不倫の背景は不要ではないか。これから不倫してやるぜ!という方がよかったのにと思う。世の既婚男性で不倫願望があるのは多分70%ぐらいだと勝手に見積もるが、実際に行動に移すのは20%ぐらいだろう。つまり、豪太はマイノリティなわけで、この点で感情移入がしづらくなる。同様にユミの年下カレシ設定も、一線を越える前ぐらいが望ましかった。
また、豪太やチカの家族が一切出てこない点も気になった。日本に限らず、恐妻家になる男性のかなり割合はマザコンの度が強いと推測される。豪太の母親が一瞬出てきて、あるいは電話やメールで「あんた、チカちゃんに迷惑かけてるんじゃないだろうね?」みたいに言う。それに対して豪太がしどろもどろで返答する。そんなシーンが欲しかった。
あとは全体のバランスか。コメディではあるのだが、笑えるシーンは序盤に集中しすぎていて、後半のシリアス展開が異様に重く観る側にのしかかってきた。このあたりは素直にアメリカのラブコメ映画の文法を参照し、採用しても良かった。
総評
観る人を選ぶ作品である。というよりも、観る側がこの作品を選ぶには、様々な基準が存在すると言うべきか。既婚男性ならば問題ない。妻が天使であろうと鬼嫁であろうと自分なりに楽しめることだろう。既婚女性も大丈夫だ。夫が輝けるかどうかは妻次第だという、ある意味ジェンダー・ロール論をバリバリに展開する本作であるが、そこは足立紳監督は心得たもの。女性かくあるべしという論ではなく、女性かくあるべしという理想形を実現できるか否かは男性側にかかっていることを密やかに、しかし高らかに宣言している。逆に言えば、このあたりのメッセージを受け取りづらい若い世代には、単なる嫌な夫婦物語に見えてしまうかもしれない。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
give a massage
マッサージする、の意。しばしば give 誰それ a massage という形で用いられる。一般的に「する」というと do を思い浮かべる人が多いが、英語で「○○する」という際には、他にもmakeやgiveが使われることが非常に多い。
give a presentation = プレゼンをする
give a speech = スピーチをする
give a big hand = 盛大な拍手をする
相手に何かをしてあげるという際にはgiveを使おう。