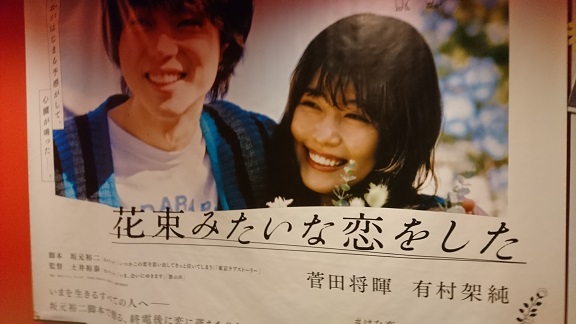あのこは貴族 75点
2021年2月28日 MOVIXあまがさきにて鑑賞
出演:門脇麦 水原希子 石橋静香 篠原ゆき子 高良健吾
監督:岨手由貴子

日本の経済的成長の停滞が続いて久しく、貧富の格差がどんどんと広がり、もはやそれが身分格差にまでなりつつあるようだ。上級国民なる言葉も人口に膾炙するようになってしまったが、そのような時代の空気を察知して本作のような作品を世に問う映画人もいるのである。
あらすじ
良家の子女として育てられてきた華子(門脇麦)は、顔合わせの当日にフィアンセと別れてしまう。次の相手を探すうちに姉の夫の会社の顧問弁護士で代議士も輩出している名家の幸一郎(高良健吾)と出会い、交際が始まる。しかし、幸一郎の影には時岡美紀(水原希子)という女性がちらついていて・・・

ポジティブ・サイド
門脇麦の感情を表に出さない演技が光る。フィアンセに顔合わせの当日にフラれたというのに、苛立ちや悲しみを一切見せることがない。家族や親族も華子を特に慰めるでもなく、サッサと次に行くべきと主張するなど非常にドライだ。そしてそのアドバイス通りに次から次へと色んな男との出会いを重ねていく華子の姿は、相手の男がどいつもこいつも社会不適合者気味なこともあり、滑稽ですらある。そんな華子がついに出会った幸一郎が、また存在感、ルックス、学歴、職業、立ち居振る舞いが完璧で、この出会いの時に華子が見せるかすかな瞳の輝きが実に印象的だった。
そんな幸一郎には、実は女の影があり、それが地方から上京してきた美紀。幸一郎に講義内容をメモしたルーズリーフを貸したところ、それが返ってくることがなかったというエピソードが印象的だ。苦学の末に慶應義塾に入学したにもかかわらず、実家の経済状態の悪化で退学。ノートもお金も時間も東京に吸われてしまったが、東京は彼女に何も与えてくれなかった・・・というストーリーにはならない。したたかに生きると言ってしまえば簡単だが、美紀が見せる生きる力、決断力、友情の深さに励まされる人は多いのではないだろうか。
二人の女性が幸一郎を間接的に媒介して出会うことになるのだが、そこにはドロドロとした女の情念のようなものはない。あるのは人間同士の真摯な向き合い方だ。幸一郎と婚約したという華子に、美紀は幸一郎とはもう会わないと伝え、実際に幸一郎との腐れ縁をスパッと断ち切ってしまう。男と女のドラマをいかようにも盛り上げられる機会を、物語はことごとくスルーしていく。それは本作が描き出そうとしているのが、男や女ではなく人間だからである。
「私たちって東京の養分だね」と呟く美紀を見て、自分も良く似た感慨にふけったことがあるのを思い出した。多かれ少なかれ、東京以外の土地から東京へと出ていった人間は、自分は東京という幻想をさらに強固なものとするためのシステムの一部にすぎないと実感することがあるはずだ。自身がマイノリティであるという自覚をもって言うが、本作は『 翔んで埼玉 』と同工異曲なのだ。そして華子も美紀も幸一郎さえも、巨大なシステムに囚われているという点では同じ人間なのだ。
敷かれたレールから外れることの困難、敷かれたレールの上を走り続けることの困難。いずれの道を往くにせよ、そうした決断にこそ自分らしさというものが宿るのだろう。生きづらさを抱える現代人にこそ観てほしいと思える作品である。

ネガティブ・サイド
慶応義塾大学という実在の大学に配慮したのだろうか。もっと『 愚行録 』のように描いてしまっても良かったはず。なにしろテーマの一側面が東京と外部。慶應内部生と慶應外部生というのは、その格好のシンボルだろう。ここのところの暗部をもう少し強調して描くことができていれば、相対的に美紀の生き方がより輝きを増したものと思う。
華子と美紀、それぞれの親友との友情をもう少し深めていくシーンがあれば尚良かった。特に、華子の親友のヴァイオリニストは美紀と幸一郎のつながりを目撃する以上に、華子と一笑友人で居続けるのだと感じさせてくれるようなシーンが欲しかった。
総評
一言、傑作である。日本の今という瞬間を切り取っていると同時に、抗いがたいシステムから抜け出し、自立的に生きようとする人間の姿を丁寧に描いている。女性ではなく、男性もここには含まれている。B’zはかつて「譲れないことを一つ持つことが本当の自由」だと歌った。その通りだと思う。これが自分の生き方だと受け入れる。そしてその通りに生きる。そうすることがなんと難しく、そして清々しいことか。2021年必見の方が作品の一つである。
Jovian先生のワンポイント英会話レッスン
set up shop
「起業する」や「開業する」の意。start one’s (own) businessという表現が普通だが、set up shopというカジュアルな表現もそれなりに使われる。これに関連するtalk shop=「仕事の話をする」という表現は『 ベイビー・ドライバー 』で紹介した。同じ表現を様々に言い換えることで、コミュニケーションがスムーズになる。